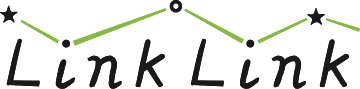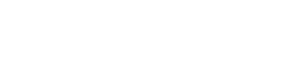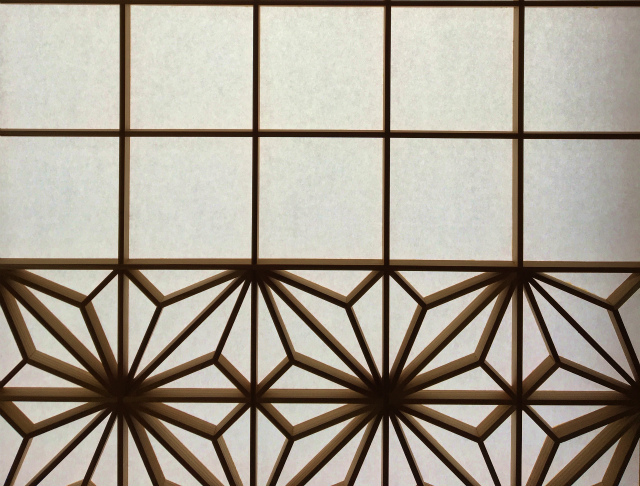長野県の南木曽町漆畑に、”木地師の里”と呼ばれるエリアがあります。木地師とは、山に入って木を切り、和製轆轤(ろくろ)を使って、木からお椀やお盆といった「木地」を作る職人のこと。
その木地師の歴史はとても古く、遡ること平安時代。第55代目天皇の文徳(もんとく)天皇の息子、第一王子の惟喬(これたか)親王が、弟との世継ぎ争いに敗れ、滋賀県の山の中に身を潜め、その地で自らろくろを発明し、家臣であった小椋大臣実秀(おぐらおとどさねひで)と大蔵大臣惟仲(おおくらおとどこれなか)にろくろを使って木地を引くことを伝授します。これが、木地師はじまりと言われています。

今回、お話をうかがった「木地屋やまと 小椋商店」の主宰 小椋正幸さんは、その家臣たちの末裔であり、1100年以上の伝統を受け継ぐ「木地師」のひとり。
正幸さんは、南木曽にある「木地屋やまと」の4代目。父である先代の小椋栄一さんから伝統工芸としての技術を継承しながらも、先代とはちょっと違う木地師としての在り方を提唱しています。
どうして、滋賀県ではなく、ここ南木曽町が”木地師の里”と呼ばれているのか。
小椋さんのお話から、長い歴史を持つ木地師と山々との深い関係と、そのルーツを探ってみました。
伝統工芸だけじゃない木地師の、ロマンあふれるお話のはじまりはじまり・・・
■みんな違う、それが自然で、それがいい器づくり
木を精一杯活かして、器を作る。
そう唱える正幸さんが作る漆器は、一つとして同じものはありません。
どういう意味かと言うと、同じ木から削り出した材料であっても、ろくろを当てた時や漆を塗った時の感覚が全く違い、その感覚を頼りにそれぞれ器を作ると別々の個性を持ったものが出来上がる。
正幸さんがそうしようと思って作っているわけじゃなく、木を大事にして作るとそういうものに仕上がっていくのだそうです。

「これが年輪ね。それで、木皮の内側の白い部分が辺材の部分です。精一杯木を活かすというのは、木の径に対して縦に木を割って、その形状に合わせて器を形どり、ろくろを当てて、まあるく削っていくとどうしてもこういう形ができるっていう。木のギリギリまで生かす仕事をしている。どうして、そんな風になったかと言うと、古いものを骨董屋さんなどで見た時に、昔は人間の都合で器を同じ形に揃えようっていう発想がなかったんだなぁって気がついて。器の面に木の肌が見えていたりする器があって、それは人間が意図的に作ったんじゃなくて、一生懸命切り倒したこの木を精一杯活かしてあげよう、より大きくしてあげようっていう意識が働いたところなんですよ。それを感じた時から、木の肌が見えてたってって別にいいじゃないかと。そういう物づくりをしようと思ったんです。」

先代 栄一さんの時代は、物を大量生産することを追い求めていた高度成長期の真っ只中で、木地屋の業界も例外ではなく、機械技術の発達によって山から木を切り出すことも容易になり、木地屋にとって良い木とは生産効率を上げられる太く大きな木でした。そこから、木を四角く大量に切り出し、木地師がろくろをかけて木地を作り、漆職人が漆を塗る。たくさんの漆器を効率よく作り出すために、いくつもある工程をわけ、流れ作業化して生産性を高めていたのを、果たしてそれでいいのか?と正幸さんは感じていました。
そんな時代がくる前の戦後昭和20年代までは、どんな仕事の仕方をしていたのか?そもそも木地師とはなんなのか?
正幸さんは、木地師のふるさとである惟喬親王ゆかりの地 滋賀県東近江市に足を運び、木地師の歴史を辿ると同時に、様々な木地師について書かれている文献やそれに関わる資料を読み、自分のルーツを紐解いていきます。
■歴史を知り、祖先を知り、自分に繋がる今を知る
滋賀県の奥永源寺地域(後に東近江市に統合)にある君ヶ畑と蛭谷という町は、木地師のふるさとと呼ばれ、君ヶ畑の大皇器地祖神社、蛭田の筒井神社は、全国の木地師の祖神の本源と定められています。
惟喬親王がろくろの技術を教えた家臣である小椋大臣実秀と大蔵大臣惟仲もこの地に住み着き、子孫に技術を継承していったことで、木地屋さんには小椋(小倉)・大蔵(大倉)姓の職人が多いそうです。
正幸さんの小椋の姓も小椋大臣からだそうで、正幸さんの父親の母方は大蔵姓だそうで、どちらもご先祖様に当たります。

後に滋賀県の地域に材料となる木がなくなったことで、木地師たちは良い木を求めて全国へ移動をはじめます。木地師たちは、2つの神社から発行された木地屋渡世の許可状と、各関所が自由に通れ全国どの山へでも入山できる往来通行手形を持ち、良い木があると聞きつけた地域へ滋賀から全国へ散らばっていったのです。
そんな全国の木地師の分布と移動の様子が書かれている「氏子駈帳・氏子狩帳」という資料。ここには、木地師が住んでいた地名や人名、家族構成、初穂料などが列記されています。実はこれは、両神社が氏子(木地師)から初穂料を徴収するために、居場所を把握しておくものとして書かれた記録だとか・・・なにはともあれ、とっても貴重な資料です。

小倉さんが、その一部を見せてくれました。分厚い冊子が上下巻あり、それぞれ小椋姓と大蔵姓のもの。明治維新前までの記録があるそうです。
記録によると、正幸さんの先祖は滋賀から奥三河の山に入り、そこから次は伊那谷へ移動していったそう。そして、明治時代から木曽に入り、定住するようになったんだとか。
その移動ルートには、昔は木の流通の盛んだった地域や良い材木が取れる山などがあったりして、そこには必ず川があったり、今でも材木屋がたくさん残っていたりなど、辿った地域を調べるとそこにドラマがあったんじゃないかと・・・なんだかロマンを感じます。

木地師が木曽に初めて足を踏み入れたのは、明治に入ってから。江戸時代、木曽は尾張徳川藩の領地だったので、木を一本切ると首が飛ぶと言われていたそうです。
明治維新以降は、皇室財産とされる御料林となり、正幸さんの先祖は「木曽に素晴らしい木があるぞ!」と聞いて、呼ばれてきたんではないかなぁ・・・と正幸さん。こうして、明治11年ご先祖さまが伊那谷から木曽へ移っていったのです。
■大切にしたい、木地師の誇りと山との繋がり
「この許可状や手形が、実際のところ本物かどうかっていう話もあって、今の歴史家の中には信じていない人もいるけれど、でもその許可状とかが通用していたから木地師は山の木を切り、山々を渡って暮らしていたんですよね。自分たちの先祖は、そうして生きてきた。」
当時の木地師の身なりは貧しく、土地に執着しないので家も立派なものは建てず、穴を掘ったところに柱を立てる掘っ建て小屋のような簡素なものだったそうです。でも木地師たちは、惟喬親王の子孫としての誇りを持って、常に生きてきたんじゃないかと正幸さんは言います。
昔の木地師は、山にある細い木と大きな木は切らずに残し、自分たちが仕事しやすいサイズのものだけを切って加工して、良い頃合いの木がなくなったら、別の山へ移っていく。そうして何十年後に、当時細かった木が太くなっていることを見越して、また戻って来たりしていました。
それは、自ずと山との自然な付き合い方を産みました。山に人が入り、適度に木が切られることで、森に光が差し、風が通る。人と山との自然なサイクルの中で、豊かな自然が残されていきました。

そんな歴史や時代を知っているからこそ、木地師としてどう物づくりと向き合うべきか。木地屋としてどうあるべきか。正幸さんは、自分の中での答えがとても腑に落ちていると言います。
「これまでいろんな時代を経た中で、やっぱり流行や世の営みに形を合わせるんじゃなくて、もっと大らかに自然に仕事をしてたっていうのを大切にしたい。」
木を精一杯活かして、器を作る。
木を目一杯大事に使ってあげる。
だから必然的に、みんなできる形が違ってくる。

「いくら同じ材料で仕事してても、物の形ってそういうところから生まれてくるのが、本来の形じゃないかなぁって。今、工芸の流れが、どちらかといえばアート的になってきている。でも、アートっていうのは自分の内面にあるものを形にして出すっていう風だから、そうじゃない部分で自分たちは仕事をしているって思う。人間の内面よりも、「木を大事にしたい!」っていう思いから生まれてくる形の方が、健康的な形というか。居心地がいい形というか。それを目指して、精一杯仕事してる。」
■先祖の歴史と一緒にあゆむ木地屋


木地屋やまとのショップの一角に、とても侘び寂びを感じる一坪の茶室があります。そこにも、正幸さんの思いが詰まっています。
「自分のおじいさんのもので、山の道具を入れておく小屋が昔あったんですよ。その小屋がまさに掘っ建て小屋で、穴を掘って、柱を刺して、釘打って、屋根つけてっていう。そういう家の建て方だったから、全部解体して、今その材料が実はお店の茶室で使われているんですよ。」

これは、その小屋に使われていた柱。
明治30年頃は、ろくろを回すのに水車を利用していたから、掘っ立て小屋はみんな川ッペリにあったんだそうです。伊勢湾台風があった時に、川の近くは危ないからみんなは上の方に避難したけど、正幸さんのおじいさんは「うちは大丈夫だから」と小椋家の小屋一軒だけは移動せず、ずっと川の近くで柱が朽ち果てるまであったんだそう。

その小屋も、人がいられるスペースは一坪の小屋だったとか。
おじいさんも、まさか茶室になるとはきっと思ってなかったんではないでしょうか?
歴史ある木地師の世界。
これは、ほんの序の口です。木曽の木のこと、漆のこと、まだまだ奥が深いんです。
ぜひ、奥木曽にあるお店で、ぜひ正幸さんの作られる器を手にとってみてください。
物の形の美しさとは、一体なんなのか。少しわかるよう気がするかも知れませんよ。